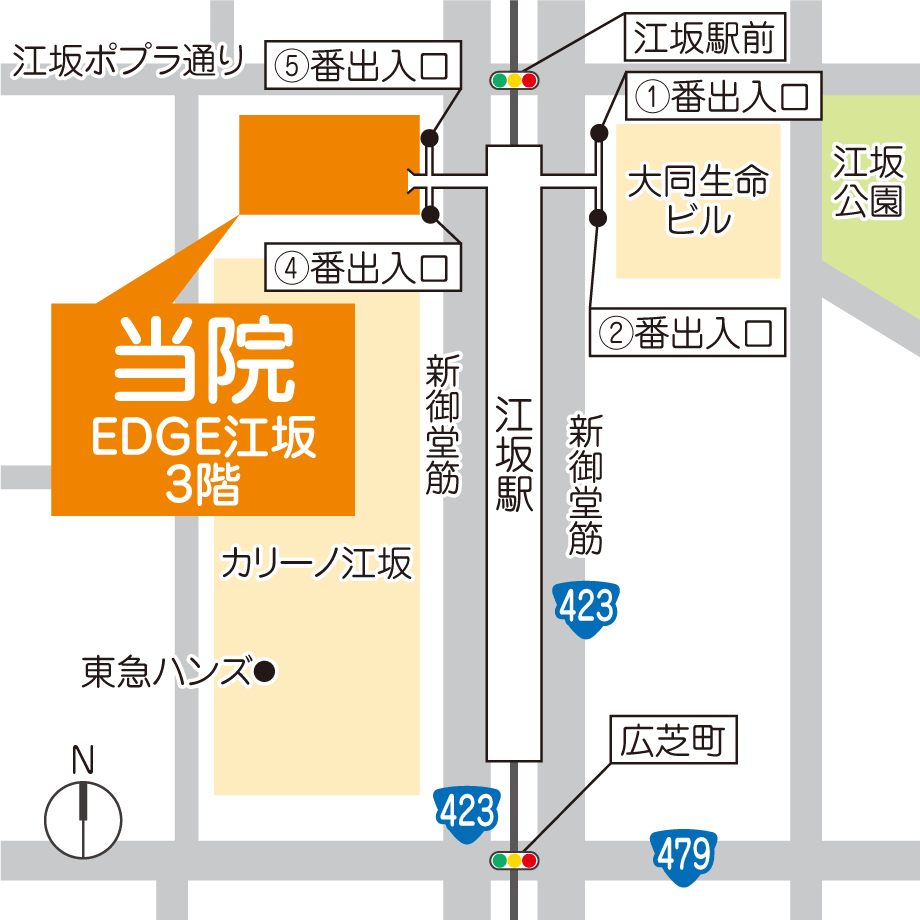強迫性障害とは
自分の意思に反して、不合理だとわかっている考えや衝動、イメージが頭に浮かんで離れない強迫観念と、手洗い、確認、順番に並べるなどの繰り返しの行動や儀式行為、数を数えるなどの強迫行為を中核症状としています。
強迫症状のために長い時間を浪費し、物に触れられなくなったり、家に閉じこもらざるを得ないこともあるため、生活に著しい支障が生じます。
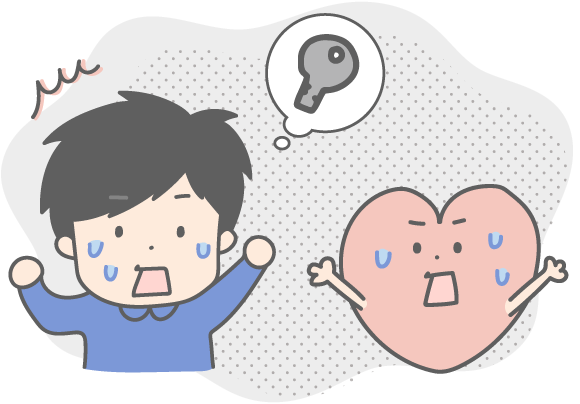
強迫性障害の原因
強迫性障害の原因については様々な面から研究されていますが、はっきりとした結論は出ていません。こだわりが強く几帳面な気質、遺伝や生育環境、脳内の情報伝達物質(セロトニン、ドパミンなど)の乱れ、感染症、神経精神疾患(チック関連)などが要因と考えられています。
強迫性障害の症状
- 長時間、何度も手洗い、入浴、歯磨きなどを続ける
- ドアノブ、電車のつり革などに触れることができない
- 戸締まり、ガスの元栓、電気のスイッチなどの過剰な確認
- 手順が儀式化し、物事が先へ進まない
- 幸運な数、不吉な数が過剰に気になる
- 物の位置や対称性にこだわり、何度もやり直す
- 物を捨てられず、過度に溜め込んでしまう
不安やとらわれから行動を起こす「認知的タイプ」以外にも、ぴったり感や前駆衝動による「運動性タイプ」や、チック関連の強迫性障害もあります。
また、これらの症状に家族を巻き込み、難治化、長期化していることもあります。
強迫性障害の治療法
治療は薬物療法と認知行動療法があります。
- 1薬物療法
-
第一選択はSSRI(フルボキサミン、パロキセチンなど)です。効果が不十分な場合には、薬剤の変更や抗精神病薬の追加などを試みます。
- 2認知行動療法
-
一般的な「認知的タイプ」の場合には、これまで回避していたことに直面化し、強迫行為をあえてしないこと(曝露反応妨害法)を継続的に練習します。
「運動性タイプ」の方には、食事・入浴・歯磨きなどの時間を設定して行う練習(ペーシング)をします。